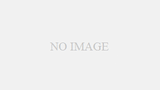向いてないと思っていた私がフリーランスになった理由
私は今、フリーランスエンジニアとして3年目を迎えています。しかし、フリーランスになる前は「自分には向いていないかもしれない」と強く思っていました。
その理由は単純で、自分には一般的に「フリーランスに必要」と言われる特性がないと感じていたからです。成果を出すスピードが特別速いわけでもなく、業務委託のエンジニアに求められがちな(と私は思っていた)「腕力の強さ」のようなものを示せる自信がありませんでした。
また、それまでずっと自社プロダクトを開発する会社にいたため、対外的なコミュニケーション経験も乏しく、それも大きな不安材料でした。
それでも私がフリーランスへの道を選んだのは、もはや「会社員として心を削るのが嫌だった」という理由からです。酷い会社だったわけではありませんが、単に所属することによるストレスが私には合いませんでした。
そんな不安を抱えながらもフリーランスになって3年目に突入。「意外となんとかなった」というのが率直な感想です。
この記事では、私自身の経験から「フリーランスに向いてない」と思い込んでいる方に、実際にはどんな感じなのか、また適性について考える別の視点をお伝えしたいと思います。
よく言われる「フリーランスエンジニアに向いてない人」の特徴

インターネットで「フリーランスエンジニア 向いてない」と検索すると、様々な「向いていない人の特徴」が出てきます。一般的によく挙げられるのは以下のような特徴です:
- 事務処理が苦手な人:確定申告や契約書の管理など、自分で事務作業をこなす必要がある
- 営業・人脈作りが苦手な人:仕事を継続的に獲得するためには人脈やセルフプロモーションが重要
- お金の管理が苦手な人:収入が安定しないため、資金計画が必要
- 計画性がない人:先を見据えた案件獲得や技術習得が必要
- 自己管理能力が低い人:誰も管理してくれないため、自分でモチベーションを保つ必要がある
- 技術の幅が狭い人:案件獲得のために幅広い技術に対応する必要がある
- メンタルが弱い人:不安定さに耐えられず、精神的に参ってしまう
- 変化に弱い人:環境や仕事内容が頻繁に変わる可能性がある
こうしたチェックリストを見ると、ほとんどの人が「自分には向いていない」と思ってしまうでしょう。実際、私自身もこのリストを見れば何項目も当てはまります。
確かに上記に当てはまらない人が向いているのは間違いないでしょう。ただ実際にやってみて思うのは「そんなに高い水準を要求されるわけではない」ということです。
実際にやってみて気づいた「向いてない」の思い込み

フリーランスになってから気づいたことは、上記のような「向いていない人の特徴」は確かに理論上は正しいのですが、実際には程度の問題であり、絶対的な障壁ではないということです。
私の場合、フリーランスになる前は「成果を出すスピードが高くない」「対外的なコミュニケーション経験が乏しい」という点で自信がありませんでした。
しかし実際に始めてみると、
- 自分のペースでも十分評価されることがわかった
- 丁寧なコミュニケーションを心がけることでクライアントに受け入れられた
- 自分なりに整理して仕事を進めることで信頼を得られた
自分が思っていた「フリーランスの理想像」と比べて自分には足りないものがあるように感じていましたが、実際の現場では私のやり方でも十分通用したということです。
「適性」より大事なこと

フリーランスに向いているかどうかを考えるとき、「適性」という言葉でまとめられがちですが、実はそれより大事なことがあると気づきました。
モチベーションの源泉
あなたのモチベーションはどこから来ていますか?
- 所属の安心感からですか?
- それとも自由に働くことからですか?
私の場合、会社にいたときは「所属のストレス」を感じており、フリーランスになってからは心理的に楽になりました。会社での連帯意識から生まれる責任感から解放されたことが、大きなメリットでした。
こうした根っこの部分の感覚は仕事をしている間、常につきまとってきます。そのためフリーランスになってからはずっと精神的に楽だなと感じています。こなしてる仕事の量はほとんど変わっていないにも関わらずです。
デメリットの受け入れやすさ
どの働き方のデメリットを受け入れられるかという問題かもしれません。
- 会社員のデメリット:所属のストレス、組織内の人間関係、裁量の少なさなど
- フリーランスのデメリット:収入の不安定さ、事務作業の負担、孤独感など
私の場合は、フリーランスのデメリットよりも、会社員のデメリットの方が耐えがたいものでした。
弱点を埋める具体的な方法
もし「フリーランスに向いていない」と思う特性が自分にあっても、それを埋める方法はたくさんあります。
事務処理が苦手な場合
- 税理士や会計ソフトを活用する
- 事務作業の代行サービスを利用する
- テンプレートやチェックリストを作って単純化する
私自身、確定申告や諸々の支払いなどの事務作業は増えました。青色での確定申告は「大変そうだな」と思っていましたが、会計ソフトを利用することでそこまで苦にはなりませんでした。
営業が苦手な場合
- エージェントサービスを活用する
- 過去の取引先や人脈を大切にする
- SNSでの情報発信を継続する
フリーランス協会の「フリーランス白書2024」によれば、最も収入が得られる仕事獲得経路は「過去・現在の取引先」(32.7%)、「人脈」(27.9%)、「エージェントサービスの利用」(13.4%)の上位3種で、全体の3/4を占めているようです。これは私自身の経験とも一致しており、必ずしも積極的な営業活動をしなくても、これらの経路を活用することで十分に仕事を得られるということです。
私自身、エンジニアの友人とエージェントサービスの紹介で案件を獲得しています。特に自分から営業をしたわけではないです。特にあてがない状態であればエージェントを使うのが早いです。
メンタル面の不安
- 貯金をある程度確保しておく
- 「上手くいかなかったらこうする」を考えておく
- 同業者やコミュニティとつながる
フリーランスになってメンタル面で負荷がかかるとすれば、金銭的な問題が大きいでしょう。そのため、ある程度貯金を確保しておくのがいいかもしれません。私の場合は、これを怠っていましたが、特に気に病むことはありませんでした。
私は上手くいかなかったら地元に戻るか、正社員にまたなればいいやと思っていました。上手くいかなかったときの安全ネットを想定しておくのは不安を解消する上で有効です。
同業者とのつながりや、コミュニティがあることで安心する人もいるでしょう。私の場合は特にフリーランスのコミュニティに入るようなことはしていませんが、前職の元同僚や趣味で知り合った友人、学生時代からの友人との交流を大切にしています。
フリーランスであること自体は大したことではない
「フリーランス=孤高の職人」「フリーランス=ハイスキルな人」といったイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし実際はもっと多様です。
私自身、上記のようなイメージを持っていた時期がありますが、エンジニアとして6年間働いた中でイメージが変わっていきました。色々な業務委託エンジニアの方と関わりましたが、意外と様々な人がいるなと感じました。
もちろんスキルがあって単価の高いフリーランスエンジニアの方と仕事をしたこともあります。他にもスキルはあるのにこんなに単価が安いの?という方もいましたし、逆にこんなに高いの?という気持ちになったこともあります(正直な話)。
「きっとこれくらいのスキルがないとフリーランスにはなれない」と勝手に思い込んでいましたが、実際には様々なスキルレベルの人がいることがわかり、自分でもできるかもと思うようになりました。
やってみないとわからない
「フリーランスエンジニアに向いていないかも」と思っていても、実際はやってみないとわからないです。
私も最初はビビっていましたが、思っていたよりもずっと普通でした。会社員としてエンジニアをやっているときと感覚的に変わらない部分は多いです。今、正社員エンジニアとして普通に働けていると感じるなら、フリーランス化も意外とハードルは高くないのではと思います。
もちろん、フリーランス化で正社員のメリット(安定した収入、福利厚生など)を手放すことになるので、そこは十分に考える必要があります。しかし、会社員という立場に不満を感じているなら、フリーランスになってメリットを感じることの方が多いかもしれません。少なくとも私はそう感じています。
大切なのは、他人の「向いている・向いていない」という物差しではなく、自分にとってどの働き方が心地よいかを見つけることだと思います。